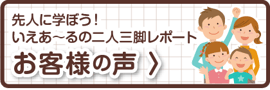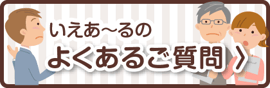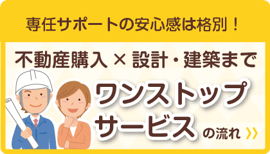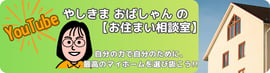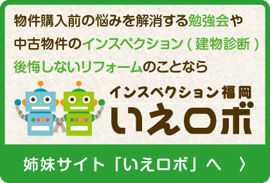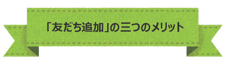4号特例の廃止

今まで、4号建築物と呼ばれてきた木造住宅(2階建て以下)は、確認申請の際、構造に関する審査を省略するという特例の対象となっていました。
2025年4月の建築基準法改正で、この4号特例は廃止。木造住宅は2号建築物の仲間入りとなり、確認申請の際、構造に関する審査が義務化されました。但し、平屋建て(200㎡以下)の住宅は、3号建築物として別の取り扱い対象となり、構造審査は免れることになりました。
構造関係図書の作成と提出
木造住宅でも、3階建ては以前から構造計算(許容応力度計算)が必要でした。それが2階建てにも拡充されるのかと当初は大騒ぎでしたが、よくよく見ると2階建ては仕様規定によるとのこと。
要は、確認申請の段階までに構造チェックを行い、申請の際には構造関係図書の提出が必要になる、ということみたいです。
構造をチェックしながら設計するのは当たり前ですから、意匠図と合わせて構造図を作成するのは理にかなっている。見積もりにも影響しますので、構造図は設計段階から必要です。
とはいえ、確認申請の審査対象となると緊張感が違います。構造図面通りの施工ができないときは設計変更申請が必要となるわけなので、確認申請に提出する段階までに全ての整合性をとり、その後の変更が発生しないように細心の注意が必要、ということになるのです。
壁量計算による耐力確認
壁量計算とは、木造建築物が地震や風などの水平方向の力に耐えられるかどうかを確認するための構造計算手法の一つです。建物の仕様と面積から必要壁量を算出し、それに対して、設計した建物の存在壁量が足りているかをチェックします。
今回の法改正で、この必要壁量の数値が大幅に上がりました。つまり、今までより壁を多く設計しないとクリアできないかもしれない…ということです。
確かに、今までの必要壁量の設定は大雑把すぎる感がありました。屋根の重さだけで規定するなんて、実際に即していません。今年3月まで使用していた数値は、1981年の新耐震基準当時のまま。44年前の数値です。この間に、外装材は厚みと重さを増し、断熱材も同様に、加重を加味する必要性が出てきました。更には太陽光発電を採用するケースも増えています。そう、省エネ政策が後押しをしてきたからです。構造に負荷がかかるのは想像できたはずですが…。
もう8月ですから、そろそろ、新基準で建てられた木造住宅が市場に出てくる頃ですね。
築浅物件と言われるものでさえ、既に、既存不適格状態にあるのかもしれません。