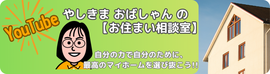中古住宅と言っても色々

「中古住宅」と一口に言っても、「新築ではない」という共通項があるだけで、その状態は様々です。新築された年度によって順守すべき建築基準も違いますし、材料の質や職人さんの技量によって、経年劣化のスピードも変わってきます。
そして、その後のメンテナンスが状態の良し悪しを左右することもあるのです。
内覧に同行すると、その家の扱われ方がよく分かります。大事にされてきたのか、いい加減に扱われてきたのか…。
中古住宅は築年数だけじゃない
私たち建築畑の人間からすると、築年数が古くても状態の良い物件もありますし、そんなに古くない物件でも酷い状態のものもあります。
ところが、不動産業界での常識は、築後25年もすれば木造住宅は価値無しと判断されてしまうのです。減価償却資産の耐用年数として、「木造住宅はそのくらいが限度」と決められているからです。
日本における滅失住宅の平均築後年数はおよそ30年と言われています。30年前と言えば既に平成の時代、そんなに昔の話じゃないですよね!?状態が良いものもたくさんあるはずなのに、年数で線引きして取り壊すなんてもったいない!
でも、逆に古すぎて、状態は悪くないものの、これからの生活を快適に過ごしていけるか?という観点で見ると無理がある物件も存在します。古いものほど価格は低めなので、飛びつきたくなるのは分かりますが、改善するために相当な費用がかかる、あるいは、費用をかけても限界がある物件なのです。
リフォームは費用対効果を考えて
場所が気に入ったのならその物件を購入することもアリですが、ここは少し冷静に、かける費用と受ける恩恵のバランスを考えた方が良さそうです。
リフォームを計画するときに考えるべきことは、「やるべきこと」と「やりたいこと」です。経年劣化の改善はもちろん、耐震性と省エネ性の確保はマスト。その上で、自分のやりたいリフォームができそうかを考えます。
限りある予算を有効に使うためには、物件購入とリフォーム計画を同時並行で考えていく必要があるのです。結構難しいんですよ!(^^)!